この資料で分かること
- 地方採用における「活路」は?
- 地方企業が採用で成功するために必要な考え方は?
- 50名以下の地方企業における「組織構築」の鉄則は?
- 「若手/中堅/管理職」の採用のコツ・やるべきことは?
フォーム送信後、すぐにご閲覧いただけます。
同業の方からの資料請求はお断りさせていただいております
ご連絡いただいた連絡先を確認させていただき、所在確認が取れない場合には資料の配付は行っておりません。
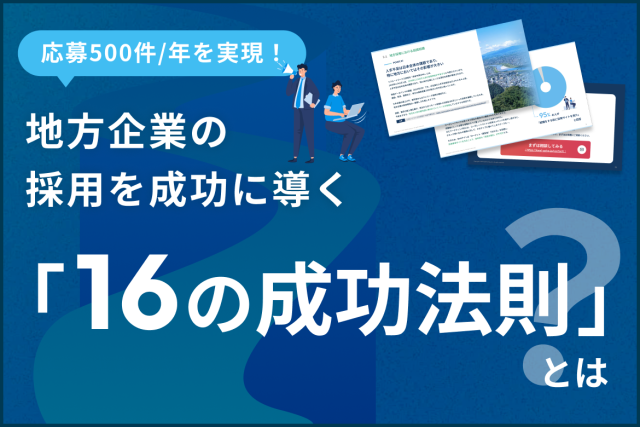

2006年に国内最大手のスカウト・ヘッドハンティング会社に入社し、スカウトエージェントとして年間準MVPを獲得。その後、岐阜県に移住し、経営コンサルタントとしての独立を経て、2013年10月に株式会社リーピーを創業。
同社では「地方の未来をおもしろくする」をビジョンに掲げ、最寄り駅から徒歩45分という立地ながらも、年間500名以上の採用応募を獲得。
現在は、採用に悩む地方・中小企業を中心に、「採用広告を一切使わない、”地方企業に特化”した採用支援」を展開。(支援実績は全国1,340社)
同業の方からの資料請求はお断りさせていただいております